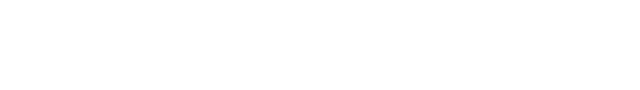産婆の弟子
令和3年11月
私の祖母は産婆(今の助産師)であり、住込で少女を産婆に育てていた。昭和の初期、まだその頃は丁度医師で言えば“あかひげ”の時代のように、師匠の手伝いをして修行していた。
太平洋戦争の始まる前頃、祖母は千葉県産婆会の副会長(当時、会長は医師?)をしてよく会議に出かけていた。それでも教育熱心な人で、お産や沐浴には必ず、見習の弟子を連れていった。暇をみては『白木産婆学』とやらテキストを持ち出して講義もしていた。弟子は夜も休めない。
祖母の部屋の敷居の外に両手をついて昼間の報告をする。「それで、プルスは?後産は?」途中で叱られて「先生、申し訳ありません」と言ってしくしく泣き出す。交代で休みの日もあったが、家には帰れず師匠の孫の子守をさせられた。その孫というのが私である。孫は“自分を可愛がってくれるオネエチャンを何であんなにいじめるんだろう”とひそかに恨んだこともあった。だが、その弟子達は立派な技量を身につけて育っていった。
後に私が開業してから、患者として来てくれた人は、中学時代の恩師の奥さんになっていた。会う度に、祖母の話をする。「私たちは何も知らない田舎娘だったのに、あなたのおばあさんは、言葉づかいから礼儀作法まで教えてくれたのよ。それはそれはとても厳しかったけれど…。おかげさまで、主人がロータリークラブの会長をした時だって、私は会長夫人としてどの奥様方にもひけをとらずにお付き合い出来たのよ。」彼女は年をとってもわが病院を自分のもののように何かとひいきしてくれた。「この病院で死ねれば本望よ。」といって、最期は本当に入院して死んでしまったのである。